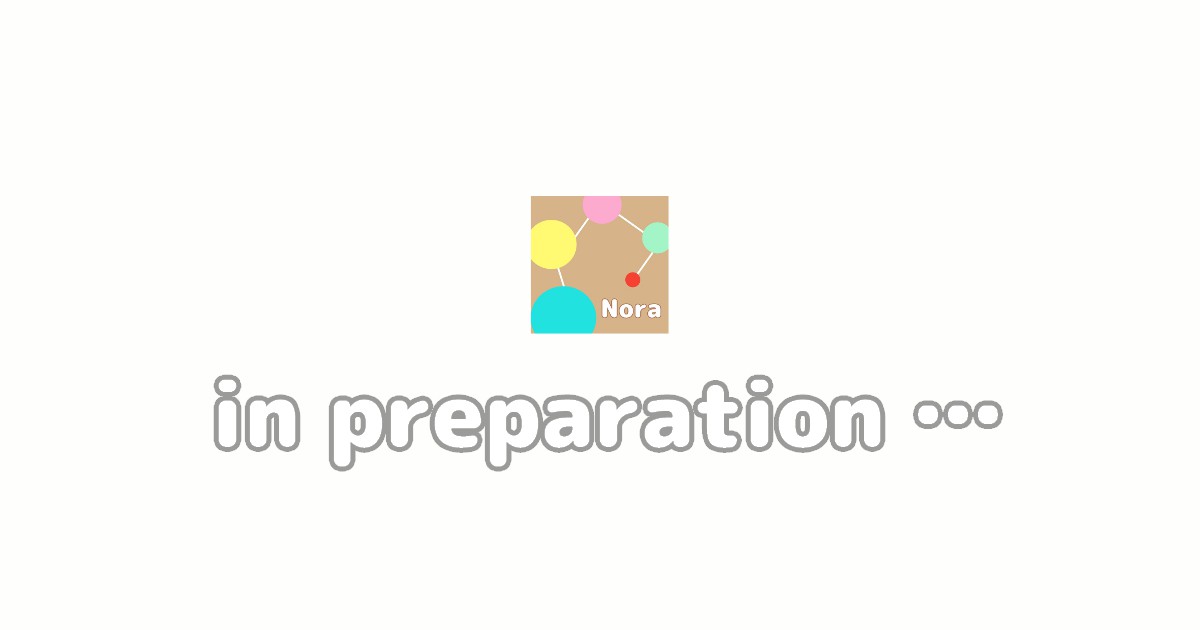当ページは、プロモーションが含まれています。
こんにちは、Noraです(^^)/
今日は、私の好きなもののひとつである「アニメ」
その中でも、おそらく私が一番最初に観たであろう「アンパンマン」について、語っていこうと思います。
「本当の正義というものは、決してかっこいいものではないし、
そのために、必ず自分も深く傷つくものです」
(絵本「あんぱんまん」より)
私は大学生の頃、母と一緒にアンパンマンの展覧会を見に行ったことがあるのですが、やなせさんのこの言葉が、一番心に刺さりました。
正義というと、
「自分にとっての敵を倒して、『もう悪いことはしない』と屈服させて、世界が平和になることだ」
と、単純に考えていたのですが、
「自分にとっては正義でも、立場が違えば、それは悪になりかねない」
ということを、教えてもらったのです。
言わずと知れた国民的キャラクター
「アンパンマン」と言えば、老若男女問わず、誰もが知っているキャラクターです。
大抵の人は、テレビや絵本などで見たことがあるかと思います。
私が幼い頃、母がテレビで放映されるアンパンマンを録画しておいてくれて、
「新しいアンパンマン、入ってるよ」と言われると、嬉しくて何度も観ていました。
今のアンパンマンのアニメは、色の彩度が高めでパキッとした印象ですが、
私が子どもの頃のアニメは、色の彩度が低くやわらかい印象でした。
大学生の頃、油彩画を学んでいた時に気がついたのですが、
私が淡い色合いやパステル系の色を好むのは、もしかしたら、
この頃に観たアンパンマンが、影響しているのかもしれません。
大人になってアンパンマンのアニメを観る機会があり、あらためて観てみたら、約10分くらいのアニメだったことに驚きました。
子どもの頃は、観るたびにすごく長く感じていたのに、不思議です。
アンパンマンの特徴のひとつは、食べ物をモチーフにしたキャラクターやお話が多いこと。
大抵どのお話にも、食べ物を作る過程が盛り込まれていて、わくわくしながら観ていました。
そしてもちろん、ばいきんまんとドキンちゃんが邪魔したり横取りに来ます。
これがあってこその、アンパンマンです。
ばいきんまんは、やさしい子!
アンパンマンの永遠のライバルである「ばいきんまん」。
彼の存在がなくては、アンパンマンの世界は盛り上がりません。
いつも悪いことや悪戯をしてみんなを困らせていますが、なんだかんだ憎めないキャラクターですよね。
子どもの頃は、ばいきんまんが最後にアンパンチをお見舞いされて、
キラッと光って消えていくと、「ああ、良かった」と安心していましたが、
大人になってからは、ばいきんまんって、実はけっこう優しい子なんじゃないかと思いました。
私が見たお話の中でそれがよく表れているのが、「ばいきんまん と シチューおばさん」ではないかと思います。
いつものように、悪いことを思いついたばいきんまんですが、今回はドキンちゃんのために奮闘し、
シチューおばさんに対して、「俺様 本当はおっかないんだぞ!」と脅しつつも、最後まで、さり気ない優しさを見せてくれます。
大人になってから、あらためてこのお話を観ると、じわっと感動して涙が出てしまいました。
「ワルは人に認めてもらえることが少ないから、つい傲慢な態度で、相手に要求をしてしまう」
と、本で読んだことがあるのですが、ばいきんまんを見ると、なんとなくわかる気がします。
それにばいきんまんって、毎回いろんなメカやマシーンを作っているし、絶対手先が器用で頭もいいですよね。
わがままを聞いてくれて、手先は器用で頭も良くて…あ、でも料理の腕は絶望的 (笑)。
魅力の尽きないキャラクターだと思います。
「こんなものは二度と作るな!」と「大好き!」の声
ここで、アンパンマンの生みの親であるやなせたかしさんについてと、
アンパンマンが誕生するまでの経緯をご紹介します。
こちらのプロフィールは、アンパンマンの展覧会に行ったときの私の記憶と、Wikipediaを参照しています。
【やなせたかしさんの Wikipedia】
やなせたかしさんのプロフィール
やなせたかしさんは、1919年に高知県で生まれました。
中学校を卒業後、
東京高等工芸学校図案科 (現:千葉大学工学部デザイン学科) に入学し、
卒業後は田辺三菱製薬に就職。
しかし、1941年に召集命令が下り、大日本帝国陸軍へ入営。
戦争で最も耐えられなかったのは、「飢え」だったそうです。
後にこの体験が、アンパンマンを生み出すきっかけにもなりました。
また、やなせさんはこの戦争で、弟さんを亡くしています。
終戦後は、高知新聞社に入社したのちに上京、三越百貨店の宣伝部で働き始めます。
1947年に、高知新聞社時代の同僚だった小松暢さんと結婚。
仕事の合間に漫画を描いては投稿を続け、1953年にフリーランスとして独立します。
独立後は、時代の変化もありテレビやラジオ、雑誌の編集、舞台美術、シナリオライター、作詞など、
漫画以外の仕事を多くこなす日々。
漫画家としての仕事はなかなか入ってきませんでしたが、
1960年代半ばに開催した展覧会をきっかけに、
あのサンリオの社長である、辻信太郎さんと交流を深めることになります。
1969年にサンリオ (当時は山梨シルクセンター出版部) から出した
「ふしぎな絵本 十二の真珠」という短編集に、
アンパンマンの前身となるキャラクターが初登場。
実は人間の姿をしていた「アンパンマン」
「ふしぎな絵本 十二の真珠 (復刻版)」
作・絵:やなせたかし
出版社:復刊ドットコム
この頃のアンパンマンは、実は人間の姿をしており、お話の内容も大人向けでした。
1973年にやなせさんは、雑誌「詩とメルヘン」と立ち上げて、
編集長として活動する傍ら、詩人・絵本作家としても活動を始めます。
この年に、1969年に発表した「アンパンマン」を、子ども向けにあらためて作り直し、
フレーベル館の月刊絵本「キンダーおはなしえほん」の1冊として発表しました。
大バッシングから国民的キャラクターに!
「絵本 あんぱんまん」
作・絵:やなせたかし
出版社:フレーベル館
こうして国民的キャラクターである「アンパンマン」が誕生しました。
しかし絵本を発表しても、すぐに受け入れられたわけではなく、
発表当初は、評論家、保護者、教育関係者から大バッシングを受け、
挙句の果てには、「こんな絵本は二度と作らないで下さい」とまで、言われたこともあったそうです。
しかし、子ども達は違いました。
大人たちのバッシングなどつゆ知らず、
絵本が出回るにつれて、「アンパンマン大好き!」の声が、次第に大きくなっていったのです。
1988年には、テレビアニメ「それいけ!アンパンマン」の放映も始まり、
今や知らない人がいないほど、有名な国民的アニメになりました。
正義と悪は、紙一重
よく「アンパンマンが、自分の顔をちぎるのが嫌」という声を聞きますが (私の母もその一人)、
やなせさんいわく、あれは「自己犠牲」の象徴だそうです。
やなせさんは戦争の経験から、
- 「自分が正しいと思っていることが、相手にとっては悪となってしまうこと」
- 「立場が違えば、正義も悪も、簡単に逆転してしまうこと」
このことを痛感したそうです。
でも、お腹を空かせている人に食べ物をあげることは、どんな人でも、どんなときでも喜ばれること。
それがアンパンマンの、「ぼくのかおを食べて」という言葉に繋がります。
優しい世界の根底にあるもの
「本当の正義というものは、決してかっこいいものではないし、
そのために、必ず自分も深く傷つくものです」
(絵本「あんぱんまん」より)
記事の冒頭でも紹介しましたが、
私がアンパンマンの展覧会に行ったときに、心に刺さったやなせさんの言葉です。
アンパンマンの明るくて優しい世界の根底には、
やなせさんの、正義への思いが強く込められているのではないかと感じました。
あと、食べ物のお話ってどうしてこうも惹かれてしまうのか…
やっぱり、私にとって食べることはひとつの幸せだから、ですかね?(笑)。
まとめ
やなせさんは、2013年に94歳でお亡くなりになりました。
生前、
「人助けをするのは好きじゃない。
一人で気楽に生きていたい人間なのに、なぜか人助けをするような巡り合わせになっている (笑)。」
とインタビューで答えていましたが、
意図したり恩着せがましい思いなくそういうことをできるのは、かえってすごいと思います。
やなせさんの故郷である高知県には、アンパンマンミュージアムと詩とメルヘン絵本館があり、
いつか必ず訪れてみたい場所のひとつです。
必ず行くぞー!٩(。•ω•。)و
それでは、最後まで読んで下さり、ありがとうございました。